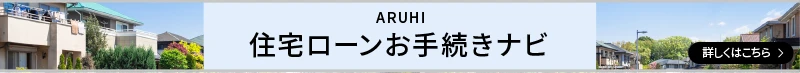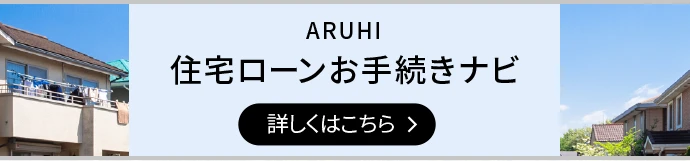住宅ローン用語集
住宅金融支援機構
住宅金融支援機構とは
住宅金融支援機構は、2007年に住宅金融公庫の業務を承継し発足した独立行政法人です。代表的な業務は、民間金融機関による全期間固定金利の住宅ローンの供給を支援する証券化業務(【フラット35】)です。その他、災害復興や災害予防に必要な住宅等の融資なども行っています。
住宅金融支援機構の事業内容は?
住宅金融支援機構では、次のような事業を行なっています。
証券化支援業務(【フラット35】)
民間金融機関が全期間固定金利の住宅ローンを供給できるように、以下の2つの方法で支援業務を行っています。
【フラット35(買取型)】
民間金融機関が【フラット35(買取型)】として貸し出した住宅ローンを債権として、住宅金融支援機構が買い受け、証券化します。住宅ローン債権を担保としてMBS(不動産担保証券)を発行し投資家に販売します。MBSの発行代金を投資家から受け取った住宅金融支援機構は、そのお金でさらに民間金融機関の住宅ローン債権を買い取るという流れになっています。
【フラット35(保証型)】
住宅金融支援機構は、利用者が返済できなくなった場合に金融機関に対して保険金を支払う住宅融資保険(保証型用)を引き受け、また、【フラット35(保証型)】の債権を担保として発行される債券等の保証も行うことで、金融機関が全期間固定金利型の住宅ローンを提供する仕組みを支援しています。
融資業務
政策的に重要であるものの、民間金融機関では対応が困難な分野について、融資業務を行っています。
たとえば、災害で罹災した住宅等の早期再建を支援する「災害復興住宅融資」や、高齢者向け住宅の供給支援となる「サービス付き高齢者向け賃貸住宅建設融資」、マンションの大規模修繕や建替えを支援する「まちづくり融資」や「マンション共用部分リフォーム融資」などがあります。
住宅融資保険事業
民間金融機関の住宅ローンで利用者が支払えなくなった場合に保険金を支払うものです。住宅金融支援機構が保険を引き受ける商品として、【フラット35つなぎ融資型】【リ・バース60】などがあります。
その他、良質住宅の普及業務、団体信用生命保険等業務、国内の住宅金融に関する調査業務など多岐にわたります。
住宅金融支援機構と銀行、何が違う?
住宅金融支援機構の目的は、「独立行政法人住宅金融支援機構法」により次のように定められています。
- 一般の金融機関による住宅の建設等に必要な資金の融通を支援する
- 国民の住生活を取り巻く環境の変化に対応した良質な住宅の建設等に必要な資金の調達等に関する情報の提供をする
- 一般の金融機関による融通を補完するための災害復興建築物の建設等に必要な資金の貸付けの業務を行う
このように一般の金融機関の住宅ローン等の支援が主であり、一部を除いて住宅金融支援機構が直接融資を行うわけではないということが、銀行とは大きく異なる点です。
住宅金融支援機構が支援することにより、金融機関が貸し出す【フラット35】と、銀行が独自で貸し出す住宅ローンは主に次のような点で違いが見られます。
| 【フラット35】 | 一般的な銀行の住宅ローン | |
|---|---|---|
| 金利タイプ | 全期間固定金利型 | 変動金利型や固定期間選択型などもある |
| 保証人 | 不要 | 多くの場合、保証会社の保証を受けられることが要件 |
| 住宅の要件 | 技術基準に適合するもの 最低床面積の条件あり |
特になし |
| 利用者の審査 | 返済負担率が基準以内であること | 年収、仕事の内容、正社員か否かなども審査の対象 |
| 団体信用生命保険 | 任意 | 団体信用生命保険に入れることが要件 |
まとめ
住宅金融支援機構には身近なところでは、【フラット35】があります。民間の銀行ローンでは借入が難しい自営業者などでも、一定の収入があり、技術基準を満たした住宅であれば借入ができるなど、住宅購入に際しては心強い存在です。
また、災害時の建物再建のための融資なども行っており、日本国民の住生活の向上を金融面から支援する独立行政法人です。
- この「用語集」は、あくまで一般的な説明をしているもので、当社の商品の説明や広告をするものではありません。
- 記事中に用いているシミュレーションの金利は試算例であり、実際とは異なります。